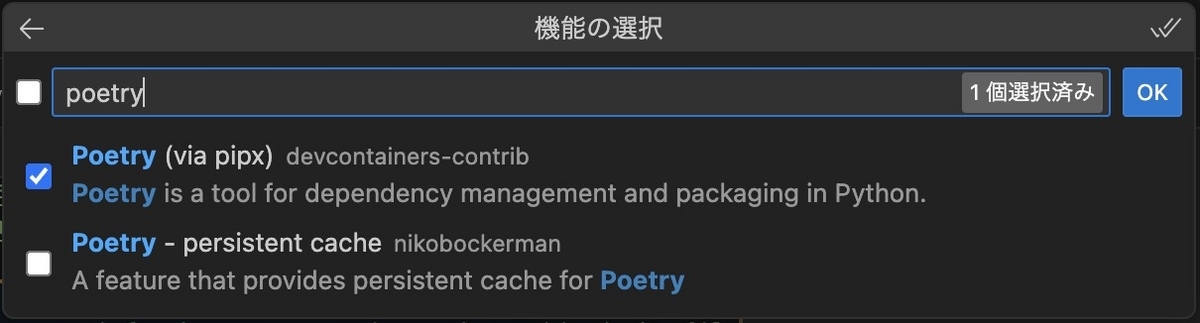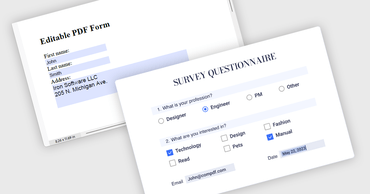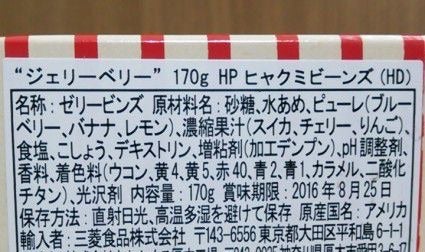概要
Go言語でRedisを使う際に選択肢に挙がるのがgo-redisです。
今回はgo-redisでTimeoutを設定する際に注意すべきことをまとめました。
手前味噌ですがBlast Radius of Failureを最小にするためにTimeoutを短くすることを1つのテクニックとしても紹介しています。
しかし短すぎるとそれはそれで問題が発生することになるので、その理由を説明します。
環境
- redis/go-redis v9.0.5
go-redisのTimeoutの種類
go-redisでは
- ReadTimeout
- WriteTimeout
- ContextTimeout
の3つを主に扱うことができます。
クライアントを生成する際に指定でき、contextについてはContextTimeoutEnabledをtrueにすることで有効化できます。
cli := redis.NewClient(&redis.Options{
Addr: "localhost:6379",
ReadTimeout: 3 * time.Second,
WriteTimeout: 3 * time.Second,
ContextTimeoutEnabled: true,
})
ReadTimeout, WriteTimeoutのデフォルト値は3秒です。
気をつけること
1. 読み取り処理でもWriteTimeoutを使う
例えばGETは読み取り処理なのでReadTimeoutのみ使うと思えますが、そうではありません。
次のようなコードを用意すると
func main() { cli := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: "localhost:6379", ReadTimeout: 1 * time.Second, WriteTimeout: 1 * time.Nanosecond, }) out, err := cli.Get(context.TODO(), "key").Result() if err != nil { fmt.Println(err) } cancel() fmt.Println(out) }
このようにwrite timeoutになります。
$ go run main.go write tcp [::1]:51732->[::1]:6379: i/o timeout
原因
Getコマンドを深ぼってみます。
func (c cmdable) Get(ctx context.Context, key string) *StringCmd { cmd := NewStringCmd(ctx, "get", key) _ = c(ctx, cmd) return cmd }
cmdableはClientにembedされています。
type Client struct { *baseClient cmdable hooksMixin }
これは初期化時にc.Processで設定されます。
func (c *Client) init() {
c.cmdable = c.Process
c.initHooks(hooks{
dial: c.baseClient.dial,
process: c.baseClient.process,
pipeline: c.baseClient.processPipeline,
txPipeline: c.baseClient.processTxPipeline,
})
}
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L621-L629
c.ProcessはClientにembedされているhooksMixinのメソッドであるc.processHookを使います。
func (c *Client) Process(ctx context.Context, cmd Cmder) error { err := c.processHook(ctx, cmd) cmd.SetErr(err) return err }
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L649-L653
c.processHookはprocessを使います。
func (hs *hooksMixin) processHook(ctx context.Context, cmd Cmder) error { return hs.current.process(ctx, cmd) }
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L171C1-L173
processは初期化時にbaseClient.processを渡しています。
c.initHooks(hooks{
dial: c.baseClient.dial,
process: c.baseClient.process,
pipeline: c.baseClient.processPipeline,
txPipeline: c.baseClient.processTxPipeline,
})
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L623-L628
baseClient.processはc._processを使います。
func (c *baseClient) process(ctx context.Context, cmd Cmder) error { var lastErr errorfor attempt := 0; attempt <= c.opt.MaxRetries; attempt++ { attempt := attempt retry, err := c._process(ctx, cmd, attempt) if err == nil || !retry { return err } lastErr = err } return lastErr }
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L370-L383
最後c._processは内部でcn.WithWriter、cn.WithReaderの両方を呼んでいます。
このためwriteのtimeoutも使われます。
func (c *baseClient) _process(ctx context.Context, cmd Cmder, attempt int) (bool, error) { if attempt > 0 { if err := internal.Sleep(ctx, c.retryBackoff(attempt)); err != nil { returnfalse, err } } retryTimeout := uint32(0) if err := c.withConn(ctx, func(ctx context.Context, cn *pool.Conn) error { if err := cn.WithWriter(c.context(ctx), c.opt.WriteTimeout, func(wr *proto.Writer) error { return writeCmd(wr, cmd) }); err != nil { atomic.StoreUint32(&retryTimeout, 1) return err } if err := cn.WithReader(c.context(ctx), c.cmdTimeout(cmd), cmd.readReply); err != nil { if cmd.readTimeout() == nil { atomic.StoreUint32(&retryTimeout, 1) } else { atomic.StoreUint32(&retryTimeout, 0) } return err }
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/redis.go#L385-L408
ただしWriteTimeoutを極端に小さくしない限りは読み取り処理においては影響はないです。
2. 書き込み処理でもReadTimeoutを使う
注意なのは書き込み側のReadTimeoutです。
次のようなコードを用意します。
func main() { cli := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: "localhost:6379", ReadTimeout: 1 * time.Millisecond, WriteTimeout: 1 * time.Second, }) out, err := cli.Set(context.TODO(), "key", "val", 0).Result() if err != nil { fmt.Println(err) } cancel() fmt.Println(out) }
このようにread timeoutが出ました。
$ go run main.go read tcp [::1]:51748->[::1]:6379: i/o timeout
原因
先程のコードが原因なわけですが、コードを見るにレスポンスを受け取る際にもこのRaedTimeoutを使っていると考えられます。
if err := cn.WithReader(c.context(ctx), c.cmdTimeout(cmd), cmd.readReply); err != nil { if cmd.readTimeout() == nil { atomic.StoreUint32(&retryTimeout, 1) } else { atomic.StoreUint32(&retryTimeout, 0) } return err }
これはローカルtoローカル通信なのでまだ良いですが、クラウドなどの通信では小さいReadTimeoutを設定していると書き込み処理においてこのエラーが発生しやすくなります。
MSET, Pipelineへの影響
例えばローカルtoローカルの通信環境において、GETが ReadTimeout: 5 * time.Millisecond で問題ないのに対し、
MSET
10件程度でread timeout
PipelineでのSET
1200件程度でread timeout
といった結果になりました。
このことからMSETやPipelineの処理は、件数によってGETよりもReadTimeoutの影響が強く出る事が分かります。
テストコード
テストコードにおいてもPing処理でread/write両方のtimeoutでエラーを発生させているので、どちらも使われているのは仕様通りと言えます。
3. Timeoutはコネクションをクローズさせる
以下の記事には、多くのDBではcontext cancelの場合はコネクションをクローズするとあります。
When context is cancelled, go-redis and most other database clients (including database/sql) must do the following:
- Close the connection, because it can't be safely reused.
- Open a new connection.
- Perform TLS handshake using the new connection.
- Optionally, pass some authentication checks, for example, using Redis AUTH command.
ref: Go Context timeouts can be harmful
そしてコネクションの再生成が必要となりオーバーヘッドが発生することで、よりTimeoutが発生しやすくなるという負のループに陥る可能性があります。
実際に検証してみました。
Timeoutしない場合
func main() { cli := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: "localhost:6379", ReadTimeout: 3 * time.Second, WriteTimeout: 3 * time.Second, }) for i := 0; i < 3; i++ { // KEYS * _, err := cli.Keys(context.TODO(), "*").Result() time.Sleep(1 * time.Second) } time.Sleep(3 * time.Second) }


このように最後の処理が完了してからコネクションがクローズされます。
またコネクションはプールで再利用されます。
ContextTimeoutする場合
しかしcontext timeoutすると、
func main() { cli := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: "localhost:6379", ReadTimeout: 3 * time.Second, WriteTimeout: 3 * time.Second, ContextTimeoutEnabled: true, }) for i := 0; i < 3; i++ { ctx, _ := context.WithTimeout(context.TODO(), 5*time.Millisecond) // KEYS * _, err := cli.Keys(ctx, "*").Result() time.Sleep(1 * time.Second) } time.Sleep(3 * time.Second) }
再利用するには適切な状態ではないと判断されコネクションは即座にクローズされます。

実コード
該当の処理はここにあたります。
func isBadConn(err error, allowTimeout bool, addr string) bool { switch err { casenil: returnfalsecase context.Canceled, context.DeadlineExceeded: returntrue }
https://github.com/redis/go-redis/blob/c0ab7815ea66b036d0cb02e2902a7820551d948a/error.go#L79-L85
func (c *baseClient) releaseConn(ctx context.Context, cn *pool.Conn, err error) { if c.opt.Limiter != nil { c.opt.Limiter.ReportResult(err) } if isBadConn(err, false, c.opt.Addr) { c.connPool.Remove(ctx, cn, err) } else { c.connPool.Put(ctx, cn) } }
ReadTimeoutする場合
じゃあReadTimeoutなどは大丈夫なのかというと、
func main() { cli := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: "localhost:6379", ReadTimeout: 10 * time.Millisecond, WriteTimeout: 3 * time.Second, }) for i := 0; i < 3; i++ { // KEYS * _, err := cli.Keys(context.TODO(), "*").Result() time.Sleep(1 * time.Second) } time.Sleep(3 * time.Second) }
こちらもコネクションがクローズされました。
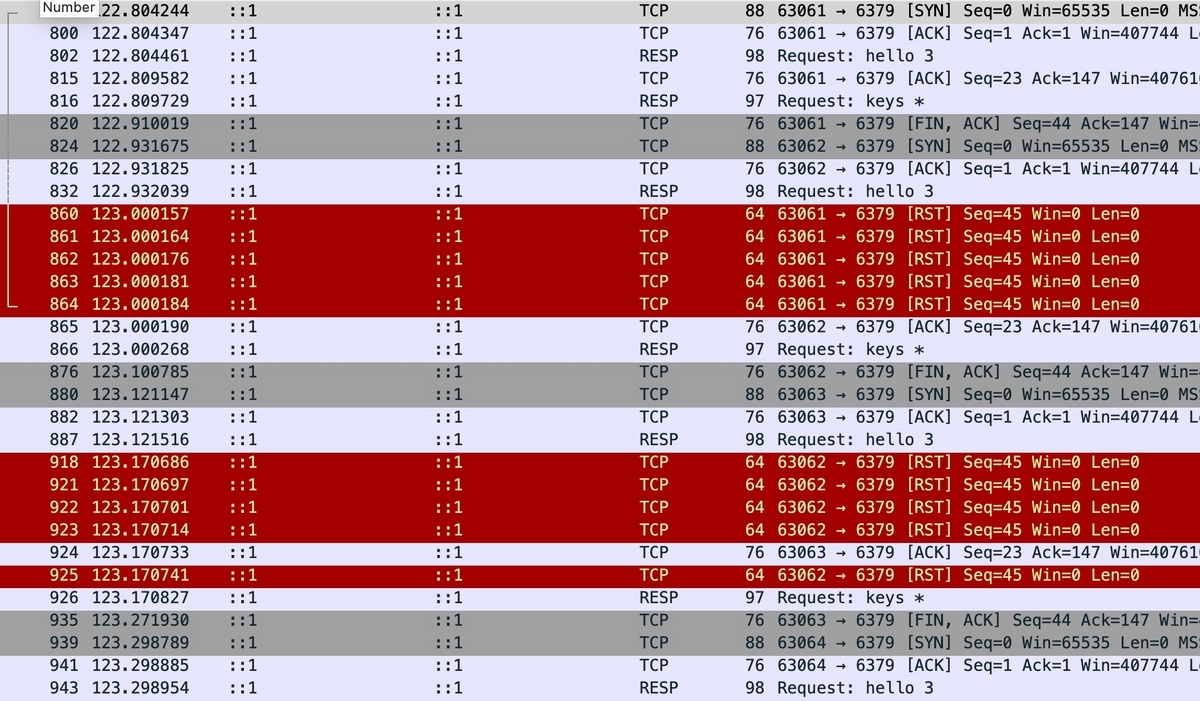
ただしcontext timeoutが全処理の合計としてのtimeoutとして扱われがちのに対し、ReadTimeoutやWriteTimeoutはコマンドは都度の通信で設定されるのでハンドリングしやすいと言えます。
対応
これまでの内容から以下のことを念頭に置く必要があります。
- 読み取り処理、書き込み処理それぞれにおいてReadTimeout, WriteTimeoutが影響する
- 特にReadTimeoutはレスポンスの取得に使われるので注意
- Timeoutが発生するとコネクションがクローズされ再利用されなくなるため、よりレイテンシが悪化しTimeoutが起きやすくなるので負のループに陥る
- Context TimeoutよりはReadTimeout, WriteTimeoutの方がオススメ
まとめ
go-redisを使う上でのTimeoutの扱い方の注意を説明しました。



















































![[ザノースフェイス] リュック バッグ シャトルデイパック Shuttle Daypack 通学 通勤 ビジネスバッグ 【SS23】 ブラック [ザノースフェイス] リュック バッグ シャトルデイパック Shuttle Daypack 通学 通勤 ビジネスバッグ 【SS23】 ブラック](http://m.media-amazon.com/images/I/31-6xU8kxHL._SL500_.jpg)